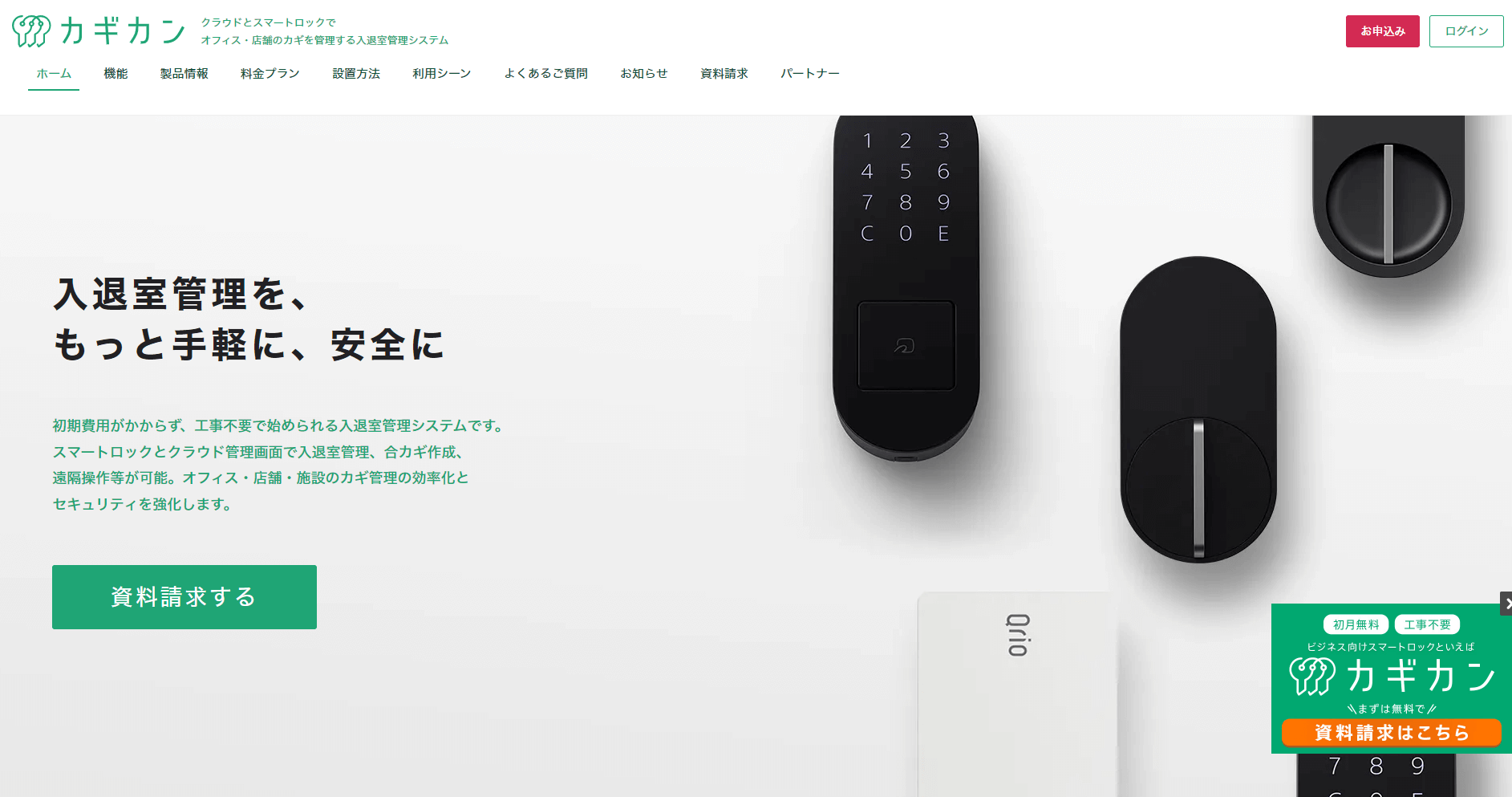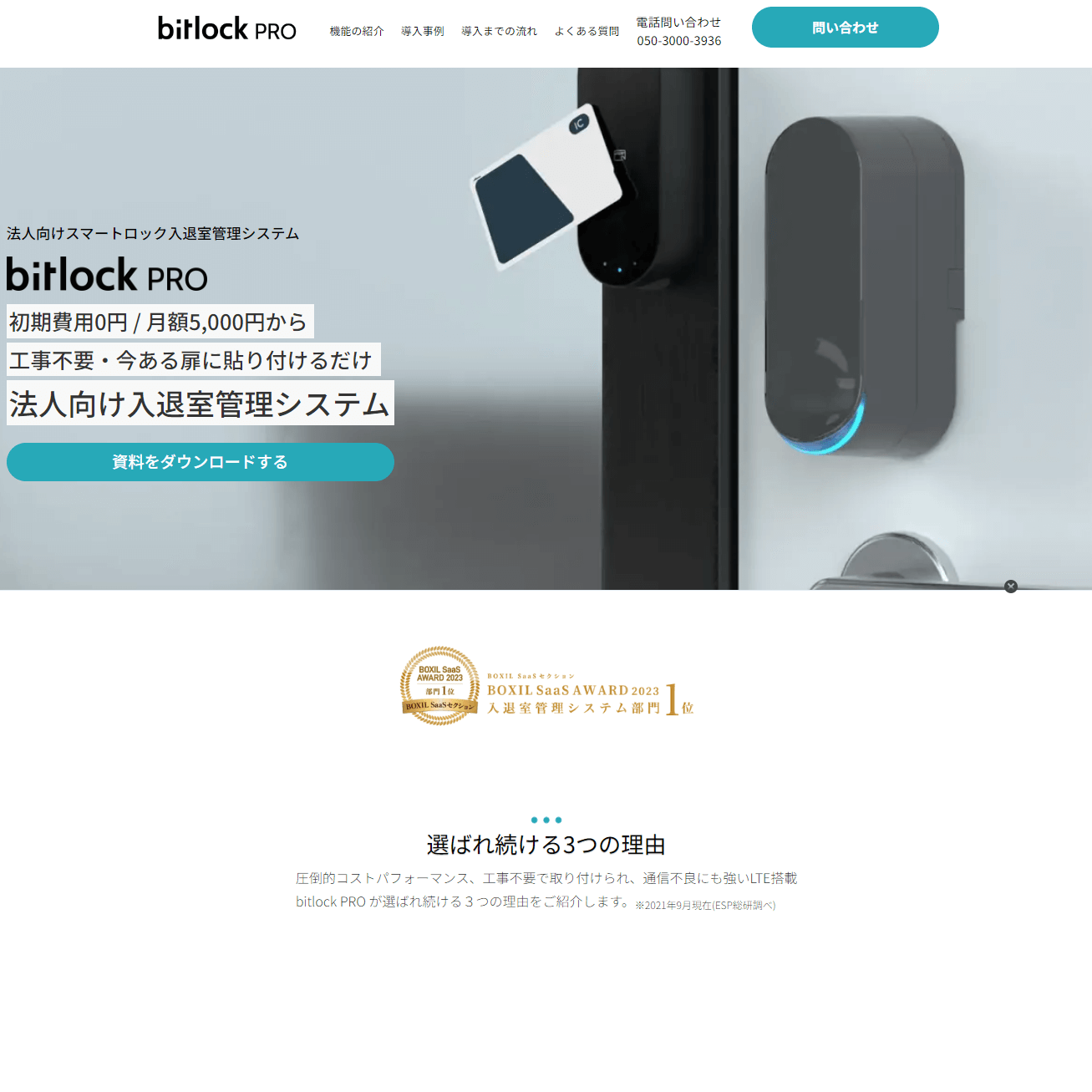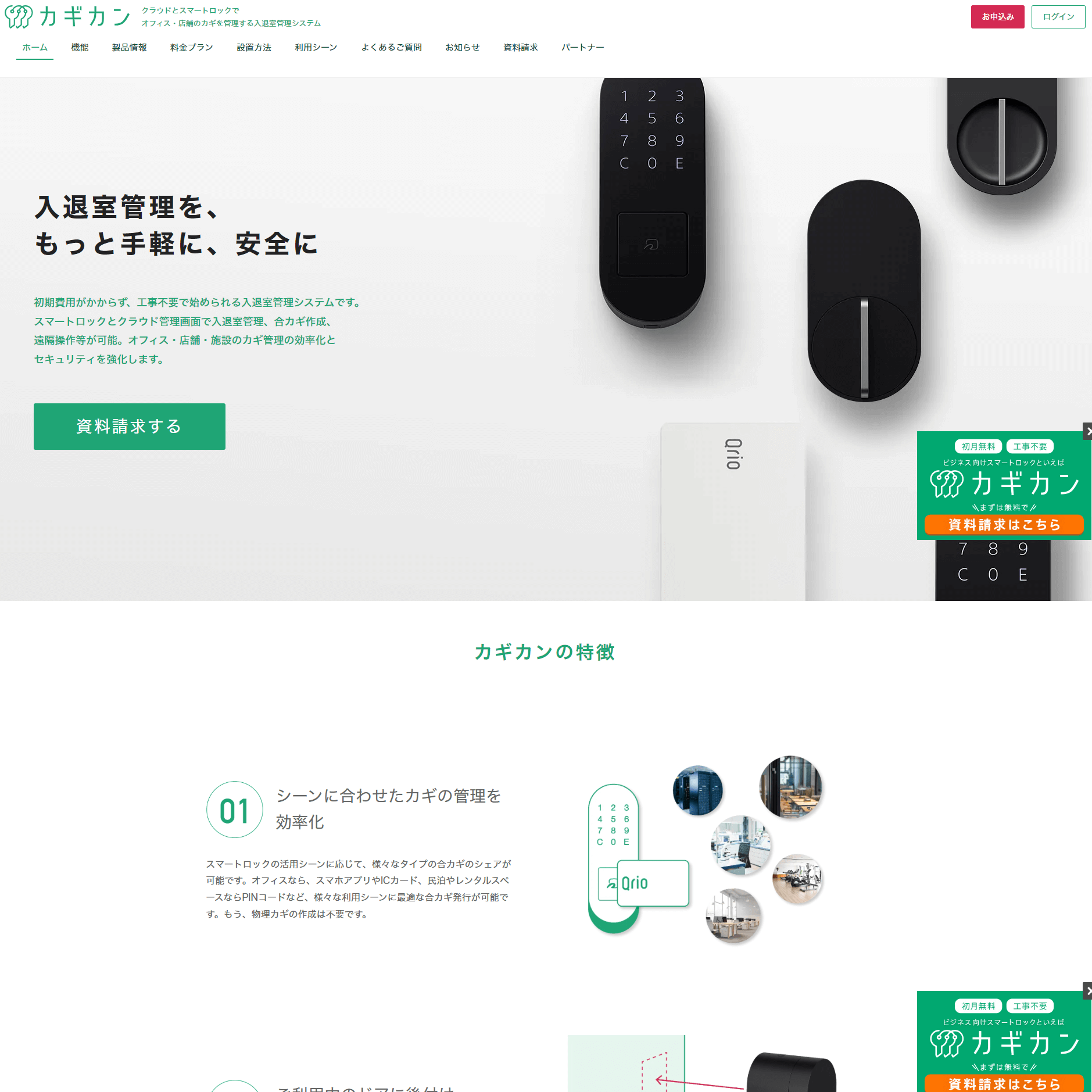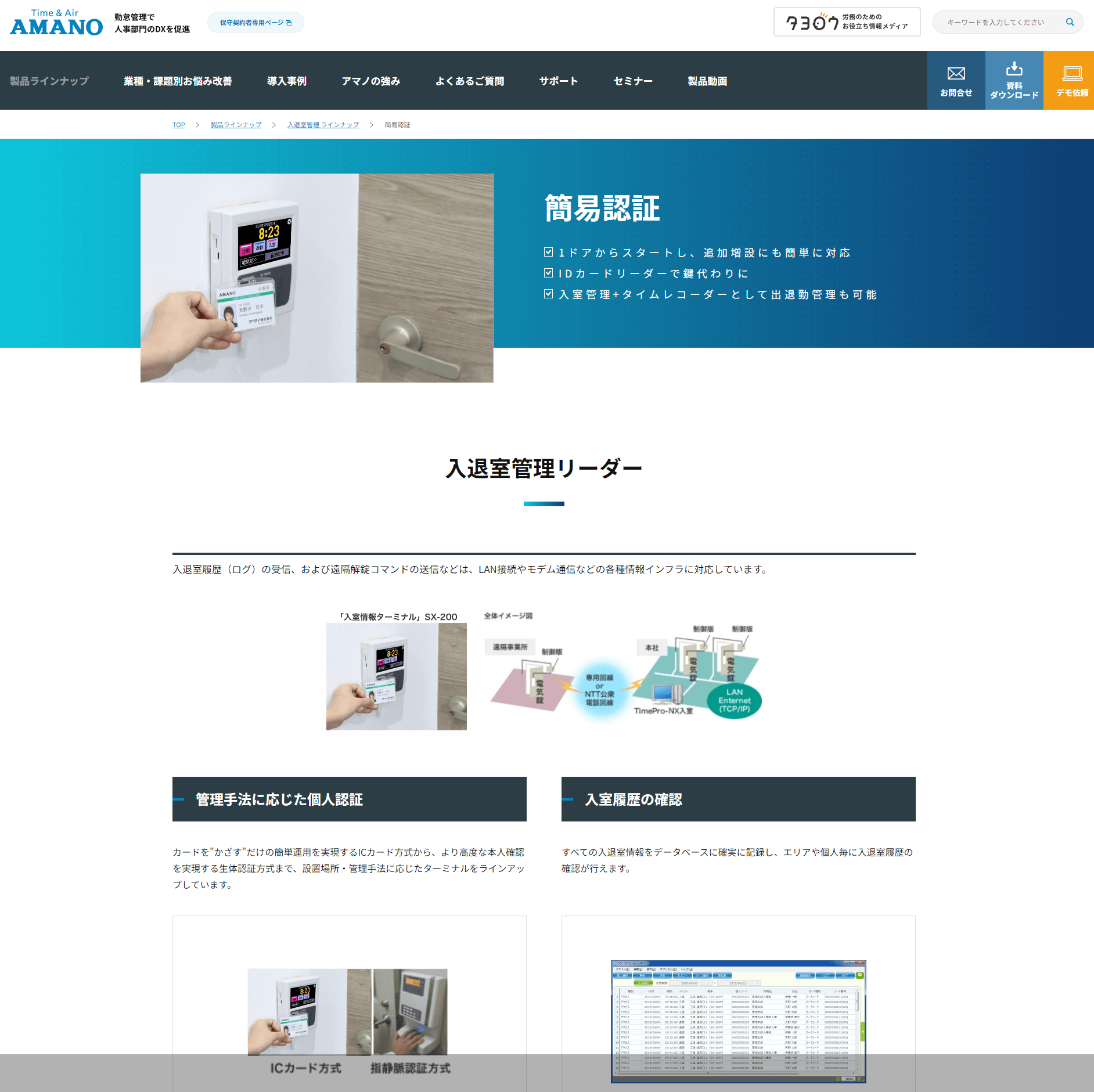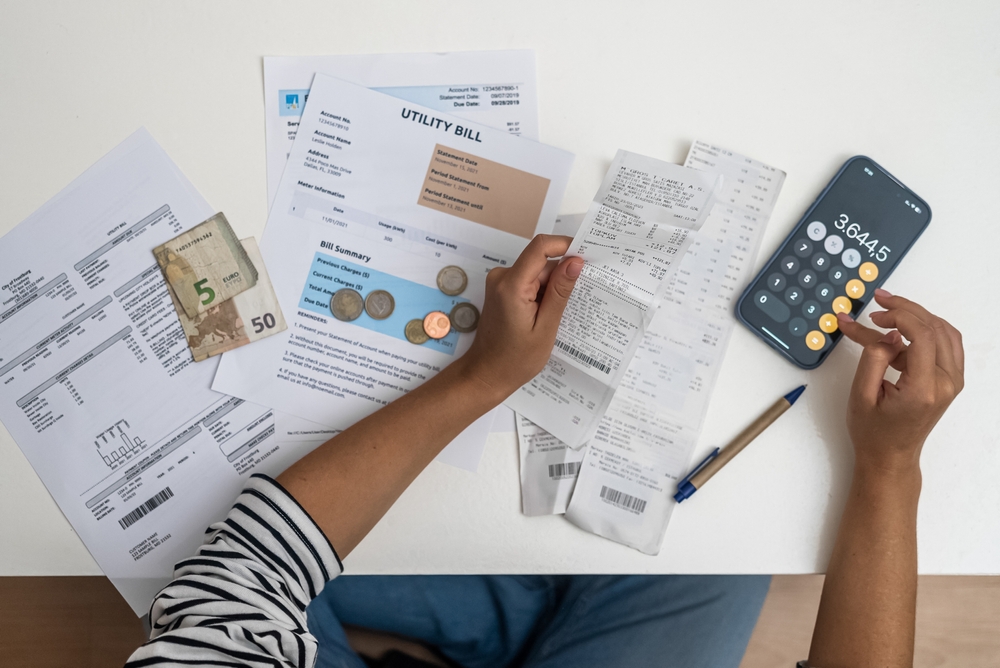はじめに
近年、働き方改革やセキュリティ意識の高まりを受け、オフィスの入退室管理は大きく見直されています。スマートフォンやICカードで施錠・解錠できるスマートロックは、もともと家庭で普及しましたが、いまはオフィス導入が急増中です。物理鍵の紛失リスクを減らし、勤怠や来訪者管理と連携して運用負荷を下げられるためです。
本記事では「スマートロック オフィス」をテーマに、特徴・費用・注意点を整理し、自社に最適な選び方をわかりやすく解説します。
結論(最初に)
●賃貸・スモールスタートなら工事不要の電子錠(後付け)で素早く導入。
●主要出入口/人の出入りが多い扉/機密室は、安定・強固な電気錠(有線)が無難。
●まずは1〜2扉で小さく試す → 効果を見て段階拡大が、コストもリスクも最小です。
選び方の4軸(この順で判断すると失敗しません)
1.工事の可否:原状回復の制約が厳しいなら電子錠、OKなら電気錠も候補に。
2.拠点数・扉数:多拠点/多扉はクラウド一元管理で付与/失効・棚卸をラクに。
3.連携の必要性:勤怠・来訪者QR・予約・カメラ・SSOなど、API対応とログ出力は必須。
4.守りの強さ:夜間無人や機密室は二重チェック(IC+暗証 等)やすり抜け防止を扉ごとに設定。
この記事でわかること
●オフィスでのスマートロックの選び方(電子錠/電気錠の使い分け)
●費用の目安と、よくある失敗と回避策
●導入チェック表と14日導入フロー(現地確認→試験導入→本番展開)
●主要製品の比較ポイント(認証方式/工事有無/API/ログ)
「スマートロックは知っているけれど、何を基準に選べばいいか」「費用やセキュリティ面が不安」という方でも、ここから読めば最短ルートで判断できるように構成しました。まずは結論を押さえ、次章の“選び方の基準”へ進みましょう。
CONTENTS
- 1 スマートロックとは
- 2 オフィス向けスマートロックの特徴(家庭用との違い)
- 3 オフィスの“選び方”基準(工事可否・拠点/扉・連携・守り)
- 4 5分でできる“選び方”チェック(そのまま埋めるだけ)
- 5 Do / Don’t(失敗しないための一言ルール)
- 6 オフィス向けスマートロックの機能
- 7 オフィス向けスマートロックの導入メリット(成果で見る)
- 8 電子錠と電気錠の違い(オフィスでの使い分け)
- 9 費用の目安(電子錠/電気錠・月額・工事)
- 10 よくある失敗と回避策(オフィスあるある5選)
- 11 まとめ
- 12 オフィス向けスマートロック主要製品の比較表
- 13 オフィス向けの入退室管理システムおすすめ7選
- 14 導入事例から見るオフィスでの効果
- 15 まとめ
- 16 【FAQ】よくある質問
スマートロックとは
スマートロックは、金属のカギを使わずにスマホ・ICカード・暗証番号・生体認証などで扉を開け閉めできる仕組みです。家庭向けの「玄関に貼るガジェット」というより、オフィスでは入退室管理の中核として使われます。ポイントは「だれが/いつ/どの扉に入れるかをルール化し、その履歴(ログ)を自動で残せる」ことです。
オフィスでの基本の動きはシンプルです。
認証(スマホやIC) → 権限の判定 → 扉を解錠 → ログ保存。
これにオートロック(閉まったら自動施錠)、時間帯ルール、**一時的な入館キーの発行(来訪者QRなど)**を重ねることで、日々の運用がグッと楽になります。
導入構成のイメージは次のとおり。
●扉側デバイス:読取機(リーダー)やサムターンを回す機器。
●中枢(コントローラ/ゲートウェイ):複数の扉をまとめる“頭脳”。有線・Wi-Fi・LTEなどでつながる中継役。
●管理画面(クラウド):ユーザー登録、権限設定、ログ確認、遠隔解錠を行う“操作盤”。
取り付け方法には大きく2タイプあります。
●電子錠(後付け):工事不要でスピード導入。賃貸や小規模に向く。
●電気錠(有線):扉に組み込み工事を行う方式。人が多く通る主要出入口や機密エリアで安定稼働・強い制御に向く。
どちらを選んでも、オフィスでは勤怠・来訪者・会議室予約・監視カメラなどと連携できるか(APIやCSV出力)、ログの保存年数、**停電時の挙動(開ける/閉める)**を決めておくことが成功のカギです。選び方や使い分けの具体例は、このあと「選び方の基準」「電子錠と電気錠の違い」で詳しく解説します。
オフィス向けスマートロックの特徴(家庭用との違い)
家庭向けが“玄関を便利に”なら、オフィス向けは“人と扉をルールで管理して、記録を残す”のが大きな違いです。だれが・いつ・どこに入れるかを役割(ロール)でまとめて付与し、ログを自動保存→検索→CSVで出せること、勤怠・来訪・予約・カメラなど社内システムとつながること、そして停電や通信断でも止めない設計が前提になります。主要出入口や機密室では、二重チェック(IC+暗証/顔)やすり抜け防止のような“強い制御”も求められます。
| 観点 | 家庭向け | オフィス向け(特徴) |
|---|---|---|
| 目的 | 玄関の利便性 | ルール管理+記録+連携 |
| 権限 | 家族単位 | 部署/役職/時間帯(ロール) |
| 履歴 | 簡易ログ | 監査向けログ(検索/CSV) |
| 連携 | 単体利用が中心 | 勤怠/来訪/予約/カメラ/SSO |
| 可用性 | 電池前提 | 停電時の開/閉を設計、UPS/オフライン |
くわしい機能は「オフィス向けスマートロックの機能」、方式の選び分けは「電子錠と電気錠の違い」で解説しています。
オフィスの“選び方”基準(工事可否・拠点/扉・連携・守り)
「どれを選べば正解?」を最短で決めるには、4つの軸だけ見れば十分です。
①工事の可否 → ②拠点/扉の数 → ③システム連携 → ④守りの強さ。順番に判断していきましょう。
① 工事の可否(賃貸・原状回復の制約を見る)
●工事できない/したくない(賃貸で原状回復が厳しい、すぐ試したい)
→ **電子錠(後付け)**からスタート。貼り付け/簡易固定で導入が早く、コストも小さめ。
注意:取り付け強度・電池運用・ガラス扉/引き戸の適合は必ず確認。
●工事できる/してよい(長期入居、主要出入口をしっかり守りたい)
→ **電気錠(有線)**が本命。安定稼働・常時施錠・二重チェックや“すり抜け防止”など強い制御に対応。
注意:配線ルート/盤置き場、夜間工事、ビル申請のスケジュールを先に押さえる。
迷ったら:重要扉=電気錠/その他=電子錠の“併用”から始め、効果を見て拡大。
② 拠点/扉の数(運用の重さと将来増を想定)
●1拠点・数扉(小規模)
→ 電子錠でも運用しやすい。最短で“鍵のデジタル化”を体験し、後で重要扉だけ電気錠へ。
●多拠点/多数扉(本社+サテライト、出入口が多い)
→ クラウド一元管理を前提に。電気錠中心だと、朝夕のピーク時でも通行が安定しやすい。
必須:ユーザー権限は人ではなく“役割(ロール)”に付与し、入社/異動/退職を自動化。
スループットの目安(朝夕の行列対策)
1人あたり立ち止まり1秒未満が理想。大人数が一斉に通る扉は、電気錠×ゲート連動が無難。
③ システム連携(“単体で便利”より“つないで便利”)
オフィスでは連携前提かどうかで選定が変わります。以下は要件表にチェック欄を作っておくと楽です。
●勤怠:入退ログを打刻補助に使う?
●来訪者/予約:事前QR→当日入館キーの流れで受付レス運用にする?
●カメラ:扉アラート時に前後クリップを自動保存?
●SSO/人事:部署/職務=ロールに自動付与/失効する?
選ぶときの条件
●API対応(Webhook/CSV出力でも可)
●ログの保存年数(例:1〜3年)と検索→CSV/PDF出力の手順
●監査で出せる項目粒度(誰/いつ/どの扉/結果)
④ 守りの強さ(扉ごとに“どこまで締めるか”)
同じオフィスでも、扉によって必要な守りは違います。扉ごとにレベルを決めると迷いません。
| レベル | 典型例 | 設定の目安 |
|---|---|---|
| 標準 | 一般フロア入口 | IC/スマホ単独、オートロック、ログ保存1年 |
| 強め | 受付レス運用/夜間出入口 | 二重チェック(IC+暗証)、来訪はQR限定、ログ保存2年 |
| 最強 | サーバ室/機密庫 | 電気錠、二重チェック固定、すり抜け防止(入→退の順守)、必要なら二重扉、ログ保存3年 |
停電・障害時(BCP)
●扉ごとに**停電で開ける(避難優先)/閉める(資産保護)**を決定。
●予備電源(UPS)とオフラインでも動く設定で“止めない”設計に。
5分でできる“選び方”チェック(そのまま埋めるだけ)
●工事:原状回復の制約(あり/なし)。→ 重要扉は電気錠?
●規模:拠点数__ / 扉数__ / 朝夕ピークの人数__。→ ゲート連動や電気錠が必要?
●連携:勤怠 / 来訪QR / 予約 / カメラ / SSO(必要なものに✓)。→ API/CSVが必須?
●守り:二重チェックが必要な扉__、すり抜け防止が必要な扉__。
●監査:ログ保存__年、検索→CSVの手順決定。
●BCP:停電時(開/閉)を扉ごとに設定、UPS/オフライン動作(要/不要)。
Do / Don’t(失敗しないための一言ルール)
●Do:重要扉から1〜2扉で試す→効果を見て段階拡大。
●Do:権限は**役割(ロール)**で管理、人事連携で付与/失効を自動化。
●Don’t:全扉を一括で置き換える(現場が混乱しがち)。
●Don’t:機能だけで選ぶ(API・ログ・停電時を先に決める)。
オフィス向けスマートロックの機能
スマートロック オフィスで大切なのは、機能そのものより「どの場面で何が効くか」です。ここでは、導入判断に直結する機能だけを、効く場面と選ぶポイントに結び付けて整理します。難しい言葉はなるべく使わず、必要なところだけ補足を添えています。
まず押さえる3本柱
●権限管理(ロール)
部署・役職・時間帯で「誰がどの扉をいつ通れるか」をまとめて設定できます。
ポイント:人事システムやシングルサインオン(SSO)と自動連携できると、入社/異動/退職の付け替えがラクです。
●ログと監査
「誰が・いつ・どの扉を・成功/失敗」を自動記録。検索してCSV(表形式)で出力できます。
ポイント:保存年数(例:1〜3年)と、監査で求められる項目が出せるかを確認。
●二重チェック&通知
ICカード+暗証のように二つの確認で安全性を上げられます。扉の開けっぱなしなどはチャット通知も可能。
ポイント:扉ごとに時間帯でオン/オフを切り替えられるかが使い勝手を左右します。
機能 → 効く場面 → 選定ポイント(実務に直結)
| 機能 | 効く場面 | 選ぶときのポイント |
|---|---|---|
| 権限の細分化(ロール/時間帯) | 異動・退職が多い、拠点が複数 | SSO/人事と自動連携、一括インポートの有無 |
| 来訪者キー(QR/期限付き暗証) | 受付レス、物理鍵の受け渡しをなくしたい | 予約システムと連携、ゾーン/時間の自動失効 |
| 遠隔操作・一括監視 | 多拠点の締め忘れ対応、臨時解錠 | クラウド管理、LTE/専用回線など通信手段 |
| 多要素認証(IC+暗証/顔) | 夜間・機密室・サーバ室 | 扉ごとに二重チェック設定、時間帯切替 |
| オートロック/スケジュール | ヒューマンエラー防止、朝夕の自動開放 | 曜日・時間の細かな設定可否 |
| API/CSV連携 | 勤怠・来訪・会議室予約・カメラ連携 | API公開(Webhook)/CSV出力の有無 |
| アラート通知(開けっぱなし/強制解錠) | その場で気づいて即対応したい | 通知先(Teams/Slack/メール)としきい値設定 |
| BCP/オフライン動作 | 停電・回線断でも止めたくない | オフラインでも動作、停電時は開ける/閉めるの事前設定、予備電源(UPS) |
補足:API=システム同士をつなぐ仕組み、CSV=表形式のデータ。どちらも「連携のしやすさ」を測る目安です。
すぐ使えるミニチェック
●権限は人ではなく“役割(ロール)”で配れますか?(入社/異動/退職の自動化)
●ログ保存年数とCSV出力の手順は決まっていますか?
●二重チェックが必要な扉と、通知したいイベント(開けっぱなし等)は整理できましたか?
●勤怠/来訪/予約/カメラとつなぐ想定があり、API/CSV要件は満たしていますか?
●停電時の動き(開ける/閉める)を扉ごとに決め、オフライン動作とUPSの用意はありますか?
オフィス向けスマートロックの導入メリット(成果で見る)
スマートロックの価値は、機能そのものより導入後に何が良くなるかで判断するのが近道です。オフィスでは、次の5つの成果が出やすく、費用対効果の軸になります。
1.鍵管理の手間とコストが減る
物理鍵の配布・回収・再発行がなくなり、棚卸も検索だけで完了。退職者の権限は即時失効でき、総務の固定作業が大幅に縮小します。
2.入退室が速くなり行列が減る
スマホ/ICで手ぶら通行。朝夕のピークでもスムーズになり、受付レス(来訪は「事前QR→当日キー」)で問い合わせも減ります。
3.不正・うっかりを防げる
二重チェック(IC+暗証など)や開けっぱなし通知で、すり抜け・締め忘れを抑止。重要扉だけ強めに設定でき、体験と安全を両立。
4.監査に強い
「誰が・いつ・どこを」を自動記録。検索→CSV/PDFで提出まで数分。Pマーク/ISMS対応の負担が軽くなります。
5.多拠点を同じルールで回せる
クラウド一元管理で付与/失効が自動化。APIやCSVで勤怠・予約・カメラともつながり、拠点が増えても運用が崩れません。
Before/After(イメージ)
| 指標 | 導入前 | 導入後 | 期待効果 |
|---|---|---|---|
| 鍵棚卸工数/月 | 6–8時間 | 0.5時間 | 検索・CSVで完結 |
| 朝の入館行列 | 5–10分 | 0–3分 | 手ぶら通行・受付レス |
| 再発行/回収対応 | 毎月発生 | ほぼゼロ | 即時失効で封じ込め |
| 監査準備 | 6–8時間 | 10–30分 | ログ出力で時短 |
電子錠と電気錠の違い(オフィスでの使い分け)
スマートロックをオフィスで使うときの最大ポイントは、「電子錠(後付け)」と「電気錠(有線)」の使い分けです。ここでは、むずかしい言葉を避けて違い→向き・不向き→決め方の順に整理します。
1. まず定義(かんたんに)
●電子錠(でんしじょう)=後付けタイプ
既存のサムターン(室内のつまみ)に貼り付けたり簡易固定して工事なしで導入。電池式が主流。
例:賃貸オフィスやサテライト拠点で“まず早く試す”ときに便利。
●電気錠(でんきじょう)=有線タイプ
ドア/枠に専用機構を組み込み、配線してコントローラで制御。安定性・防犯性に強い。
例:本社エントランス、サーバ室など“止められない/強く守りたい”扉。
メモ:どちらもスマホ/IC/暗証などで解錠できますが、耐久性・制御の幅・安定性に差があります。
2. ちがいがひと目で分かる表
| 観点 | 電子錠(後付け・電池) | 電気錠(有線・コントローラ) |
|---|---|---|
| 導入スピード/工事 | 早い(工事不要) | 工事あり(配線・盤設置) |
| 安定性/通行スピード | 中(混雑時にムラも) | 高(ピーク時も安定) |
| セキュリティ制御 | 基本機能中心 | 強い制御(二重チェック/すり抜け防止 等) |
| 運用(電池/保守) | 電池交換が必要 | 有線給電・保守で長期運用 |
| BCP(停電/障害) | 機種による(電池残量に依存) | 停電時の動きを扉ごとに設計(開/閉) |
| 初期費/月額(目安) | 初期 0〜5万円/扉、月 4,000〜8,000円 | 初期 20〜50万円/扉、月 1〜2万円 |
| 向いている場所 | 賃貸・小規模・試行導入 | 主要出入口・人の出入りが多い扉・機密室 |
3. オフィスでの使い分け(具体例)
●本社エントランス/フロア入口
来客・出社ラッシュなど通行量が多い → 電気錠で安定。ゲートと連動させると行列が減ります。
●サーバ室/機密書庫
強い守りが必要 → 電気錠+二重チェック(IC+暗証/顔)。すり抜け防止(入→退の順番ルール)も有効。
●会議室ゾーン
利便性重視。予約時間だけ開放する運用なら電子錠でも可。混雑が多い場合や共連れ対策が必要なら一部を電気錠へ。
●サテライト/短期利用の拠点
まず早く/低コストで始めたい → 電子錠。のちに主要扉だけ電気錠へ段階移行が現実的。
4. 失敗しない決め方(3ステップ)
1.工事の可否(賃貸・原状回復の条件)
工事不可 → 電子錠から。
工事可 → 次へ。
2.扉の用途と人の流れ(ピーク/機密/無人時間)
通行量が多い/強い守りが必要 → 電気錠。
通行が少ない/利便重視 → 電子錠でも。
3.運用と連携(勤怠・来訪・予約・監査)
連携前提・監査が多い → API/ログ出力を満たす構成で、主要扉は電気錠中心。
まずは導入体験 → 電子錠でPoC(1〜2扉)→効果を見て拡大。
5. よくあるつまずき → こうすればOK
●電池切れ/取り付け強度(電子錠)
→ 電池残量アラート・交換ルールをSOP化。重いドア/ガラス扉は対応可否を事前確認。
●ピーク時に遅い/共連れ(電子錠)
→ ラッシュが多い扉は電気錠へ。すり抜け防止は入→退の順番ルール/二重扉で。
●工事の段取り(電気錠)
→ 配線ルート/盤置き場/夜間工事/ビル申請を前倒しで調整。1扉の試験導入→段階拡大が安全。
●停電・障害時に止まる(両者)
→ **停電時の動き(開/閉)**を扉ごとに決め、予備電源(UPS)とオフライン動作を準備。
6. ミニチェック(導入直前に)
●工事の可否は? → 重要扉だけでも電気錠にできる?
●朝夕ラッシュ/機密室はある? → 電気錠が必要?
●勤怠/来訪/予約/カメラと連携する? → API/ログは満たす?
●停電時に開ける/閉めるを扉ごとに決めた? → UPS/オフライン設定は?
●まず1〜2扉で試す段取りはできた?
賃貸や小規模は電子錠で素早く始め、主要出入口や機密室は電気錠で“止めず・強く”運用。まず1〜2扉の試験導入→効果を見ながら段階拡大が、オフィスのスマートロックでは最短の正解です。
費用の目安(電子錠/電気錠・月額・工事)
オフィスでスマートロックを導入する際に一番気になるのが「いくらかかるのか」です。ここでは代表的な2タイプ、**電子錠(後付け)と電気錠(有線工事型)**の費用レンジを整理します。金額は一般的な相場で、製品・導入規模・工事条件により変動する点をご承知おきください。
1. 電子錠(後付け・電池タイプ)
●初期費用:0〜5万円/扉
(貼り付け式や簡易固定のため工事不要。スターターパック的に導入可能)
●月額費用:4,000〜8,000円/扉
(クラウド利用料・管理画面・サポートを含むケースが多い)
●特徴:
賃貸やスモールスタート向け
原状回復が厳しいオフィスでも導入しやすい
電池交換や取付強度の確認は必要
2. 電気錠(有線・工事型)
●初期費用:20万〜50万円/扉(施工費込み)
(ドアや壁に穴を開け、配線してコントローラに接続する工事が必要)
●月額費用:1万〜2万円/扉
(クラウド利用料+保守契約。規模が大きいほど割安になるケースあり)
●特徴:
本社エントランスやサーバ室など、主要出入口向け
耐久性・安定性に優れ、混雑時もスムーズ
二重チェックやすり抜け防止など強い制御に対応
工事の段取り(配線ルート、夜間作業、ビル申請)を要確認
3. トータルコストで見るのがコツ
●初期費用+月額利用料+保守契約+アップデート費用を含めた総額で比較すること。
●高リスク扉から段階導入すると、投資効果を早めに実感できます。
例:鍵管理工数(棚卸6時間→0.5時間)、再発行・回収コスト、監査準備時間などを削減できるため、実質的な回収期間は短くなるケースが多いです。
まとめ
●電子錠=初期コストが軽く、スモールスタートや賃貸オフィスに最適。
●電気錠=初期投資は大きいが、安定性とセキュリティを重視する中〜大規模オフィス向け。
●自社の扉ごとの重要度と運用体制を整理し、段階的に選んでいくのが最短ルートです。
よくある失敗と回避策(オフィスあるある5選)
スマートロックは便利で効率的ですが、準備や運用を誤ると「デメリット」と感じやすいポイントがあります。実際には、事前に想定し、ちょっとした工夫をすれば多くの失敗は回避可能です。ここではオフィスでよく起きる5つの失敗例と、その対策を紹介します。
1. 電池切れで扉が開かない(電子錠の場合)
●失敗例:電子錠タイプで、電池が切れて出入りできなくなる。スマホ型でも、利用者のスマホ電池切れで入室できないトラブル。
●対策:電池残量アラート付きの製品を選ぶ/電池交換ルールをSOPに組み込む。重要扉は電池式ではなく電気錠を選んで安定性を確保。
2. 工事・原状回復の想定不足(電気錠の場合)
●失敗例:配線工事や壁の穴あけが必要だと知らず、賃貸ビルで導入できなかった。
●対策:事前にビル管理会社へ確認・申請し、原状回復条件を把握。主要扉だけ電気錠にして、他は電子錠で補う“併用”が現実的。
3. 朝夕ラッシュで通行が遅い
●失敗例:電子錠をエントランスに導入したら、朝の出社時に行列ができてしまった。
●対策:通行量の多い扉は電気錠+ゲート連動で処理速度を確保。ログが必要な扉はクラウド連携で検索→CSV出力まで確認。
4. 鍵の受け渡しがゼロにならない
●失敗例:来訪者や業者対応で結局物理鍵を渡している。
●対策:**一時キー(QRや期限付きPIN)**を発行できる製品を選ぶ。来訪者管理システムと連携すれば「事前登録→当日キー→自動失効」で受付レスを実現。
5. ログが不十分で監査に使えない
●失敗例:誰が通ったかは残るが、「成功/失敗」「どの扉か」の粒度が足りず監査で指摘を受けた。
●対策:保存年数(1〜3年)・検索性・出力形式を必ず確認。監査提出の実績がある製品を選び、事前にサンプルCSVを出して試す。
まとめ
「デメリット」と言われる多くは、実際には**“想定不足による失敗”**です。
●電池式は電池交換ルールで回避
●電気錠は工事・申請の事前確認で回避
●通行量の多い扉は電気錠で安定性を確保
●来訪者は一時キー発行で物理鍵をゼロに
●監査はログ保存年数・出力形式を必ず確認
これらを押さえれば、スマートロックはオフィスにとって「効率化+セキュリティ強化」の強力なツールになります。
オフィス向けスマートロック主要製品の比較表
複数のサービスがあり選びにくい場合は、一覧比較が役立ちます。以下に主要製品をまとめました。
| 製品名 | 初期費用 | 月額費用 | 認証方式 | 向いている規模 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| iDoors | 工事必要20万〜 | 1.1万円〜 | 暗証番号/ICカード/スマホ/顔認証 | 中〜大規模オフィス | 電気錠で安定稼働、複数拠点をクラウド一元管理 |
| ALLIGATE | 工事必要20万〜 | 1.65万円〜 | 暗証番号/ICカード/スマホ | 中規模 | LTE内蔵、勤怠連携や防犯カメラ連携が可能 |
| カギカン | 工事不要0円 | 4,500円〜 | 暗証番号/ICカード/スマホ | 小〜中規模 | 初期費用ゼロ、導入スピードが早い |
| bitlock PRO | 工事不要0円 | 5,000円〜 | スマホ/ICカード/暗証番号/顔認証 | 小〜中規模 | LTE標準搭載、拡張オプション豊富 |
| Akerun | 工事不要/要工事 | 1.75万円〜 | スマホ/ICカード/暗証番号/NFC | 小〜大規模 | 後付け型の先駆者、クラウド連携に強い |
| アマノ | 工事必要30万〜 | 要問い合わせ | ICカード/暗証番号/生体認証 | 大規模オフィス・工場 | 勤怠システム連携、災害時一斉解錠機能 |
| SECURE AC | 工事必要30万〜 | 要問い合わせ | 顔認証/ICカード/スマホ/QR | 大規模オフィス・研究施設 | AI顔認証・多拠点無制限、セキュリティ最高水準 |
オフィス向けの入退室管理システムおすすめ7選
idoors

idoorsのおすすめポイント
様々な認証リーダーに対応!ニーズに合わせた対応が可能!
さまざまな業種や規模のオフィスに対応できるよう、柔軟なシステム設定が可能!
導入前後のサポート無料! ヒアリング~設定までしっかりフォロー!
idoorsの基本情報
| 会社名 | 株式会社エーティーワークス |
| 住所 | 東京本社:〒106-6137東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー37F |
| 電話番号 | 03-3497-0505 |
| 電源の種類 | 電気錠 |
| 解錠方法 | 暗証番号、ICカード、スマートフォン、生体認証 |
| 価格 | 1万1,000円〜※電気錠のため初期費用は別途 |
導入事例
-

引用元:https://idoors.jp/株式会社SmartHR様- 利用者数
- 300人~
- 導入目的
- セキュリティ強化/入退ログの把握
-

引用元:https://idoors.jp/株式会社生活総合サービス様- 利用者数
- 51人~100人
- 導入目的
- セキュリティ強化/入退ログの把握/既存システムのリプレイス/顔認証の入退
-

引用元:https://idoors.jp/ゾーホージャパン株式会社様- 利用者数
- 101人~300人
- 導入目的
- 入退ログの把握/自社システムとの連携/複数拠点の一括管理
idoorsは、解錠・施錠の動きを電気信号によって行う電気錠タイプの入退室管理システムであり、電池式ではないのが特徴です。電源からの配線で動くため、取付に工事が必要になりますが、安定稼働ができ、さらに防犯性が高いなどのさまざまなメリットがあります。
いつでもクラウドの管理ツールで記録を確認できる
ドアの開閉がクラウド管理できるようになり、しかも複数の拠点の管理方法を一元管理できるようなります。
充実機能で課題を解決!
idoorsで入退室管理できるようになれば、ISMS、Pマークも取得も可能であり、勤怠管理もより効率的にできる様になるのです。
idoorsの最大の魅力と言えるのが抜群のセキュリティ機能です。管理画面からさまざまな情報を把握でき、アルタイムで入退室や在室状況をいつでもチェック可能です。
さらにユーザー単位で入退室できるドアの制御が可能なので、気密性が高いようなデータを保管する部屋に導入するものおすすめでしょう。クラウド型入退室管理システムであり、拠点が離れていても一元管理できるのがidoorsです。
電気錠タイプだからこそのメリットとは
WEB上の管理画面より遠隔で解錠も可能なので、急な解錠申請および予定外の訪問にも即時対応できます。顔認証にも対応しており、マスクしていても認証可能です。非接触認証が可能なので、衛生面にも優れています。
ALLIGATE

ALLIGATEのおすすめポイント
専門の作業員が責任をもって設置!
社内ネットワークの構築不要!
導入~運用まで手厚くサポート!
ALLIGATEの基本情報
| 会社名 | 株式会社アート |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-25-11 五反田一丁目イーストビル |
| 電話番号 | 記載なし |
| 電源の種類 | 電気錠 |
| 解錠方法 | 暗証番号、ICカード、スマートフォン |
| 価格 | 1扉あたり1万6,500円 ※電気錠のため初期費用は別途 |
導入事例
-

引用元:https://alligate.me/akippa株式会社- 利用者数
- 50人~299人
- 導入目的
- 入退室管理/セキュリティ強化/社員のタイムコスト意識にも好影響
-

引用元:https://alligate.me/株式会社ミュートス- 利用者数
- 10人~49人
- 導入目的
- 最新機器の導入/入退室・勤怠管理
-

引用元:https://alligate.me/株式会社ランディックス- 利用者数
- 50人~299人
- 導入目的
- セキュリティー強化/入退室管理一元化/手軽なシステムの導入
セキュリティ専業メーカーのクラウド型入退管理システムがALLIGATEです。瞬時に開場でき電池交換が不要でWi-Fi環境も不要、駆けつけサポートもあり、スマホアプリにも対応しているといったさまざまなメリットがあります。
セキュリティ専業メーカーのシステムだから高機能
セキュリティ専業メーカーだからこその高いセキュリティ性に注目です。両面テープで取り付けるだけの製品ではなく、落ちてしまったり剥がれてしまったりする心配はありません。専門の作業員が責任を持って設置してくれるので安心です。
一元管理可能なハイセキュリティ環境をつくる
ALLIGATEは、LTE内蔵の通信機器を利用したクラウド型のサービスです。社内ネットワークへ接続したり、拠点間のネットワークを構築したりする必要はありません。煩雑な手続き不要で、一元管理可能なハイセキュリティ環境を作れるのです。
勤怠管理システムと連携することで、ALLIGATEで取得した入退室ログを出退勤情報として自動送信できます。予約システムとの連携時には、予約完了時に入室可能なカギを発行してくれるなど、さまざまな機能も兼ね備えています。
さらに防犯カメラとの連携も可能で、遠隔管理やALLIGATEのAPIを活用し自社システムと連携することも可能です。
全国どこでも手厚くサポートしてくれる
初めての入退室管理リスステムの導入となると、分からないことだらけで不安に感じることもあるでしょう。その点、ALLIGATEでは、24時間365日のサポート体制を構築しています。万が一の故障の際には製品保証もあるので、余計なコストがかかることもありません。
しかも、契約期間中の故障は経年劣化が原因であったとしても無償で機器交換してくれます。サポートも日本全国対応なので安心です。
カギカン

カギカンのおすすめポイント
設置はドアに簡単貼付けるだけ!
オートロック機能搭載! カギの締め忘れによる盗難・情報漏洩リスクを防止!
最短3営業日で導入可能!
カギカンの基本情報
| 会社名 | Qrio株式会社 |
| 住所 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-3-4 東新産業ビル3F |
| 電話番号 | 050-3187-7481 |
| 電源の種類 | 電子錠(電池錠) |
| 解錠方法 | 暗証番号、ICカード、スマートフォン |
| 価格 | カギカンコンソールのみ 月額4,500円~ カギカンBasicプラン 月額5,900円~ カギカンProプラン 月額7,300円~ ※利用者料金は利用人数20人までは無料となり、21人目から100円/人で追加費用 |
導入事例
-

引用元:https://kagican.jp/株式会社コスモスさま- 利用者数
- 5人~10人
- 導入目的
- 入退室履歴の取得/履歴の長期保存/施錠忘れ
-

引用元:https://kagican.jp/株式会社ナインブロックさま- 利用者数
- 10人~20人
- 導入目的
- 従業員数に対する合カギの不足/テレワーク時における煩雑なカギの受け渡し
-

引用元:https://kagican.jp/リンクウィズ株式会社さま- 利用者数
- 10人~50人
- 導入目的
- 物理カギの不足/カギを受け渡す手間/入室時・退室時の履歴把握
初期コストを重視しているなら、カギカンがおすすめです。工事不要で始められる入退室管理システムであり、スマートロックおよびクラウド管理画面で入退室管理や合鍵作成、遠隔操作などができます。より効率的にオフィスなどを運営していきたいと考える方に適しているのがカギカンなのです。
シーンに合わせてカギの管理を効率化
スマートロックの活用シーンはさまざまであり、そのさまざまなシーンに対応できるのがカギカンです。さまざまなタイプの合鍵のシェアが可能であり、オフィスならスマホアプリやICカードが利用でき、民泊およびレンタルスペースであれば、PINコードなど利用心に最適な合鍵を発行できるのです。
いつ・誰が入退室したか確認できる
セキュリティ機能もしっかりとしており、カギカン管理コンソールでカギの解施錠履歴およびドアの入退室履歴が残ります。管理画面からの複数ドアの一元管理も可能です。ドアが閉まったタイミングでオートロックする機能もあるため、利用者の鍵の閉め忘れによる盗難および情報漏洩のリスクも低減できます。
工事費無料!低コストで利用できる
カギカンは、初期導入費用、工事費用は無料です。初期費用がかからず、さらに利用開始月は無料期間なので、コストゼロでお試し利用できるのです。それでいて複数ドアに対応しているので、とりあえず入退室管理システムを導入したいと考えている方に利用に適しています。
bitlock PRO

bitlock PROのおすすめポイント
初期費用 0 円・月額 5,000 円〜。99 % のサムターンに貼り付けるだけ
12 種類以上の解錠方法(ICカード・テンキー・スマホ・顔認証オプションなど)
LTE モデルを標準搭載しており停電や社内ネットワーク障害時でも安定稼働
bitlock PROの基本情報
| 会社名 | 株式会社ビットキー |
| 住所 | 〒104‑0031 東京都中央区京橋3‑1‑1 東京スクエアガーデン14 |
| 電話番号 | 050‑3000‑3936 |
| 電源の種類 | 電子錠(電池式) |
| 解錠方法 | スマートフォン、ICカード、暗証番号、顔認証(OP) |
| 価格 | 月額5,000円〜/扉、初期費用 0 円 |
bitlock PROは工事不要で後付けできる法人向けスマートロックです。クラウド管理画面から権限の即時付与・剥奪、入退室ログ確認が行え、Pマーク・ISMS 取得の実務をサポートします。LTE 通信内蔵ゲートウェイが標準付属のため、VPN 構築や Wi‑Fi 整備が難しいサテライトオフィスにも導入しやすく、顔認証や自動ドア連携など拡張オプションも充実しています。
アマノ

アマノのおすすめポイント
リアルタイム通信で履歴を即時取得
選べる 11 種の認証方式(ICカード・暗証番号・生体など)
勤怠システム TimePro‑VG/NX とシームレス連携
アマノの基本情報
| 会社名 | アマノ株式会社 |
| 住所 | 〒222‑8558 神奈川県横浜市港北区大豆戸町275番地 |
| 電話番号 | 045‑401‑1441(代表) |
| 電源の種類 | 電気錠(有線給電) |
| 解錠方法 | ICカード、暗証番号、生体認証、機械警備連動 ほか |
| 価格 | 要問い合わせ(システム構成により変動) |
TimePro‑XG 入退室は、勤怠・人事ソリューションで定評あるアマノが提供する電気錠型システムです。2ドアを 1 制御盤で管理できる拡張性と、10,000 件のユーザーデータ/50,000 件のオフライン履歴保持に対応。災害時には自動一斉解錠や在席確認が可能で、製造業・医療機関など高い可用性が求められる現場で採用されています。既存の美和ロック・ゴール社製電気錠との互換性も高く、段階的な導入にも適しています。
Akerun
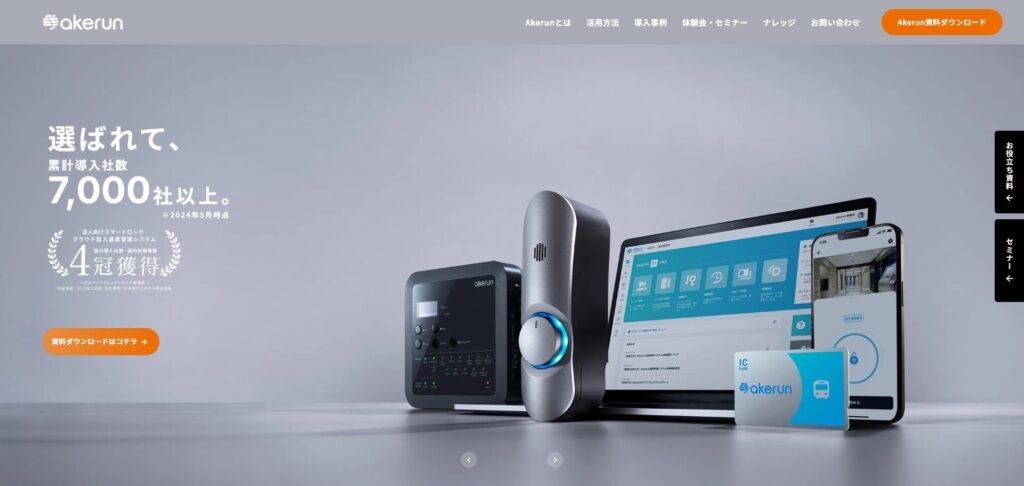
Akerunのおすすめポイント
後付け型スマートロックのパイオニア
クラウド&API 連携が豊富
1 台あたり月額 17,500 円のレンタルプラン
Akerunの基本情報
| 会社名 | 株式会社Photosynth(フォトシンス) |
| 住所 | 〒108‑0014 東京都港区芝5‑29‑11 G‑BASE田町15F |
| 電話番号 | 03‑6630‑4585 |
| 電源の種類 | 電子錠(電池式)/電気錠制御オプション |
| 解錠方法 | スマートフォン、ICカード、暗証番号、NFC |
| 価格 | 月額17,500円〜/扉(レンタルプラン) |
Akerun は 2015 年に世界初のクラウド型後付けスマートロックとして登場しました。管理コンソールから扉・拠点・ユーザーを無制限で追加でき、API で Slack や Google Workspace とも連携。ログは ISMS 対応フォーマットでエクスポートできるため監査負荷を削減します。ハンズフリー解錠や Apple Watch 対応など UI/UX の良さも評価が高く、300 名超のオフィスから小規模コワーキングまで幅広く導入されています。
SECURE AC
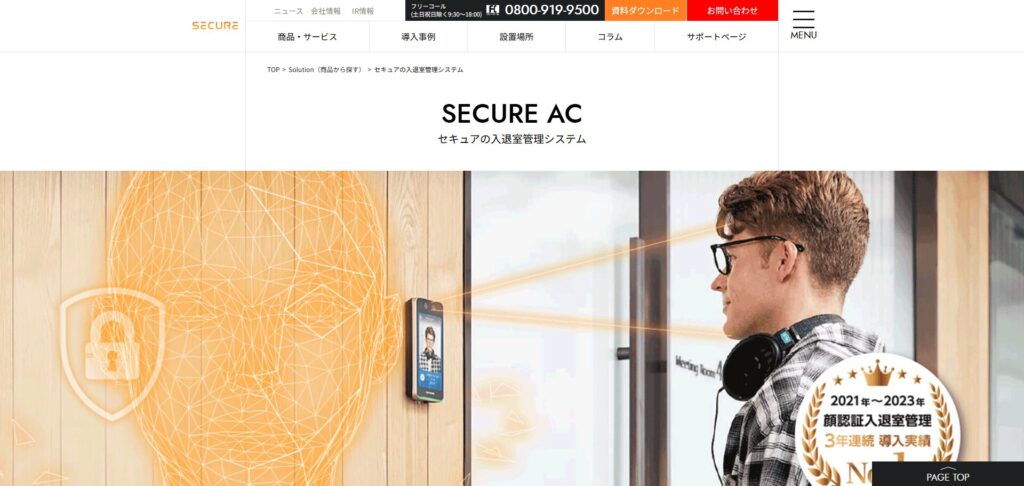
SECURE ACのおすすめポイント
AI 顔認証・指紋・IC・スマホ・QRまで対応するマルチ認証
拠点・ゲート数無制限の一元管理
Starter 〜 Enterprise まで 6 階層のプランを用意
SECURE ACの基本情報
| 会社名 | 株式会社セキュア (SECURE, INC.) |
| 住所 | 〒163‑0220 東京都新宿区西新宿2‑6‑1 新宿住友ビル20F |
| 電話番号 | 03‑6911‑0660 |
| 電源の種類 | 顔認証、ICカード、スマートフォン、QR/PIN |
| 解錠方法 | スマートフォン、ICカード、暗証番号、NFC |
| 価格 | Starter 〜 Enterprise:すべて要問い合わせ(ユーザー数・デバイス数で変動) |
SECURE AC は「監視カメラ × AI 解析」で培った画像認識技術を活かした入退室プラットフォームです。クラウド越しに全ゲートの稼働状態をモニタリングし、異常時は管理者へ即時アラート。勤怠・BEMS・警備システムとの双方向 API で、扉が開いた瞬間に照明・空調を連動させるスマートビル運用を実現します。3 年連続で入退室管理カテゴリ国内シェア No.1 を獲得しており、大規模オフィスや物流倉庫、研究施設での採用実績が豊富です。
導入事例から見るオフィスでの効果
実際にオフィス向けスマートロックを導入した企業の事例を見てみると、特に中規模〜大規模のオフィスでは大きな成果が得られています。ここでは代表的なケースをご紹介します。
事例1:300名規模のIT企業(iDoors・電気錠タイプ)
・勤怠管理システムと連携し、打刻業務を完全自動化
・出退勤の記録が正確になり、残業申請や労務管理の透明性が向上
・複数拠点をクラウド上で一元管理できるため、管理部門の負担も大幅に軽減
▶ 電気錠タイプのiDoorsなら、安定稼働と高度なセキュリティを両立できるため、社員数が多いオフィスや複数拠点を抱える企業でも安心して運用できます。
事例2:50名規模のスタートアップ(電子錠タイプ)
・物理鍵の受け渡しを廃止し、アプリ権限の付与だけで入室可能
・テレワーク社員の利便性が向上し、鍵管理コストを削減
事例3:レンタルオフィス運営会社(電子錠+クラウド管理)
・利用者に有効期限付きPINコードを自動発行
・無人での会議室・個室管理が可能となり、稼働率が改善
このように、中規模以上のオフィスでは「iDoors」など電気錠タイプのスマートロックが特に効果的です。安定した運用と高いセキュリティに加え、クラウドによる拠点横断の一元管理が可能なため、成長フェーズの企業に最適な選択肢となります。
まとめ
オフィスにおけるセキュリティ強化や入退室管理の効率化を考えるうえで、「オフィス スマートロック」は非常に魅力的な選択肢となり得ます。物理鍵が不要になることで、煩雑だった鍵管理を一気にデジタル化でき、部外者の不正侵入リスクや社員の鍵紛失リスクを大幅に軽減できます。
また、勤怠管理システムやセキュリティシステムとの連携によって、打刻漏れの防止や従業員の入退室データの正確な取得が可能となり、業務効率も格段に上がるでしょう。一方で、工事コストや月額利用料、バッテリー切れなどの注意点もあるため、メリットとデメリットをしっかり比較検討することが大切です。
導入を決める際は、自社オフィスのドア形状や求めるセキュリティレベル、従業員数、運用体制などを整理し、最適なスマートロックを選びましょう。実際に複数のメーカーやサービスの見積りを取り、機能や導入費用、サポート体制を総合的に比較すると、より納得感のある選択ができます。企業規模や事業内容によって必要なセキュリティレベルは異なるため、しっかりと要件を明確化し、導入後に想定されるメリットとコストを見極めてください。
【FAQ】よくある質問
- オフィス向けスマートロックの導入費用はどのくらいかかりますか?
- 導入費用は電子錠と電気錠で大きく変わります。電子錠は工事費がほぼ不要なため、製品本体が数万円~数十万円程度で済むケースが多いですが、電気錠はドアや壁に配線を通す施工が必要となるため、数十万円~100万円前後の予算が見込まれることもあります。さらに、クラウドサービスの月額利用料や保守費用がかかる場合もあるので、必ず見積りを複数社から取りましょう。
- スマートロックは停電時や電池切れ時でも解錠できますか?
- 多くのスマートロック製品には、緊急時の物理鍵やバックアップ電源が用意されています。電子錠タイプの場合は電池切れに備えて、外からモバイルバッテリーで給電して開錠できる仕組みを持つものもあります。電気錠タイプは建物の非常用電源などに接続している場合が多いため、停電時にも一定時間は稼働できる設計が一般的です。導入前に必ず非常時の対応方法を確認しましょう。
- 一度導入したスマートロックを他のオフィスへ移設できますか?
- 「電子錠」タイプであれば、両面テープやネジでの固定が主なので比較的容易に取り外して移設できます。ただし、「電気錠」タイプはドアや壁を加工しているため、移設には再び工事が必要となり、同じドアでなければ取り付けが難しい場合もあります。移転やリニューアルの可能性があるオフィスでは、導入時に施工コストや移設リスクも検討しておくと安心です。
- スマートロックで勤怠管理や打刻を完全に代替できるのでしょうか?
- オフィス向けスマートロックの多くは、出入りの履歴をクラウド上に記録し、勤怠管理システムと連携できるAPIを持つものがあります。これらを活用すれば、打刻専用のシステムやタイムカードを使わずとも、社員の出退勤記録を自動取得することが可能です。ただし、社員が扉を開けずに内線や別ルートから入室するなど、運用上のイレギュラーを想定する必要もあります。完全な代替を目指すなら、オフィスレイアウトや運用ルールの整備が不可欠です。
- セキュリティ面で特に注意すべき点は何でしょうか?
- スマートロック導入後も、セキュリティポリシーの策定や周知徹底が非常に重要です。たとえば、テンキー認証の場合は定期的に暗証番号を変更する、ICカードを紛失したら即時に権限を無効化する、管理者アカウントのパスワードを強固にするなど、人間側のセキュリティ意識が欠かせません。また、ベンダーが提供するソフトウェアのアップデートを怠ると脆弱性を突かれる恐れがあるため、アップデートのスケジュールやサイバーセキュリティ対策にも気を配りましょう。