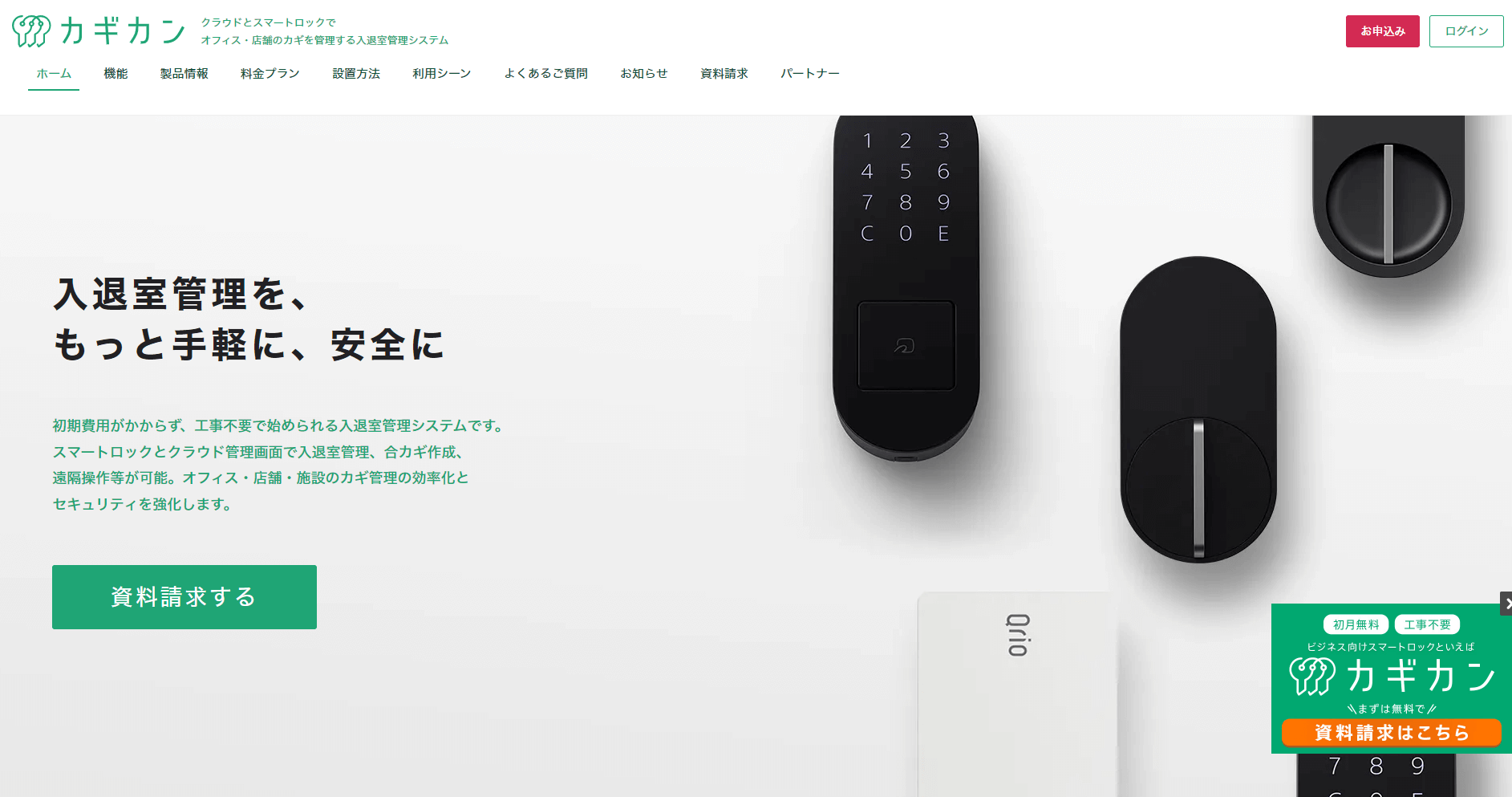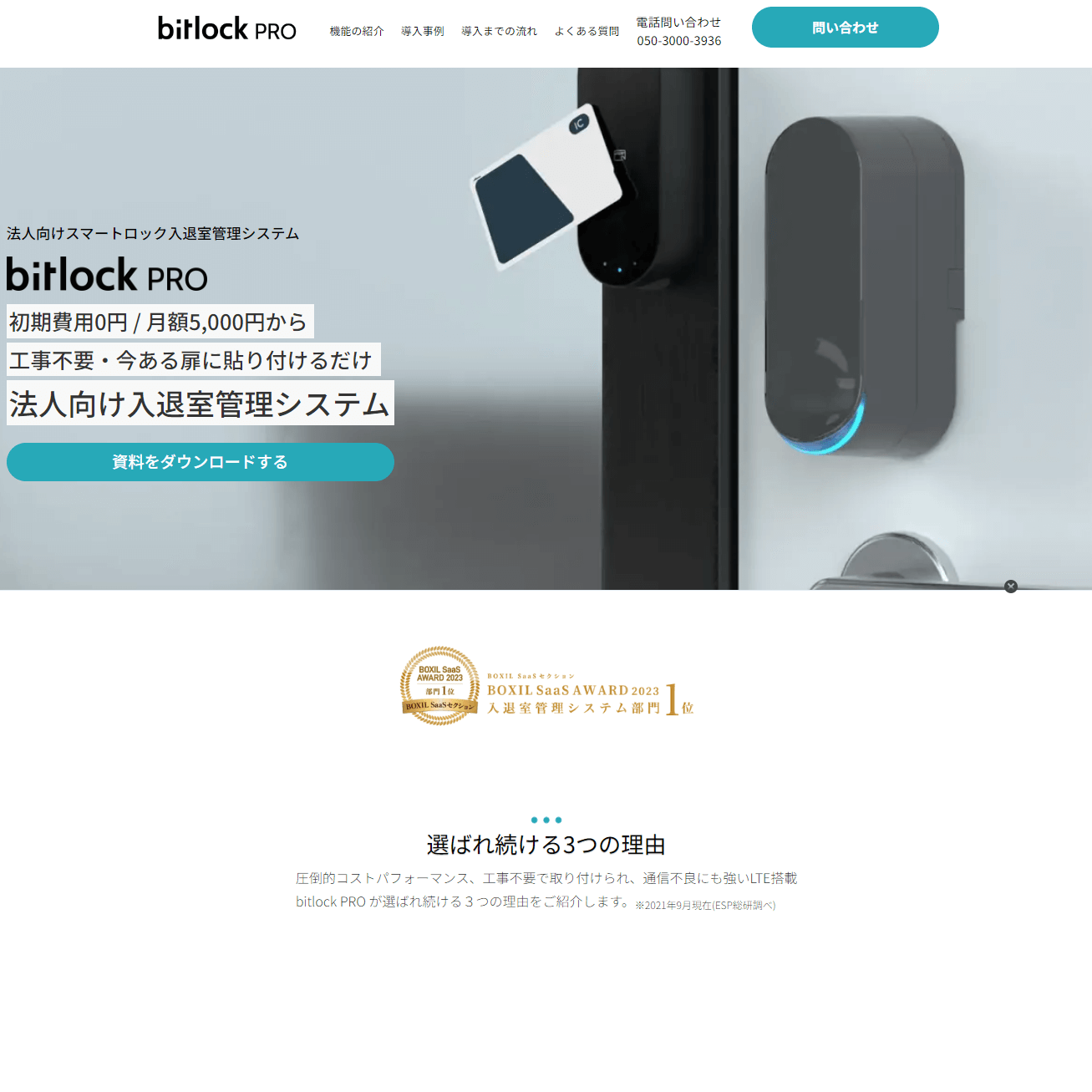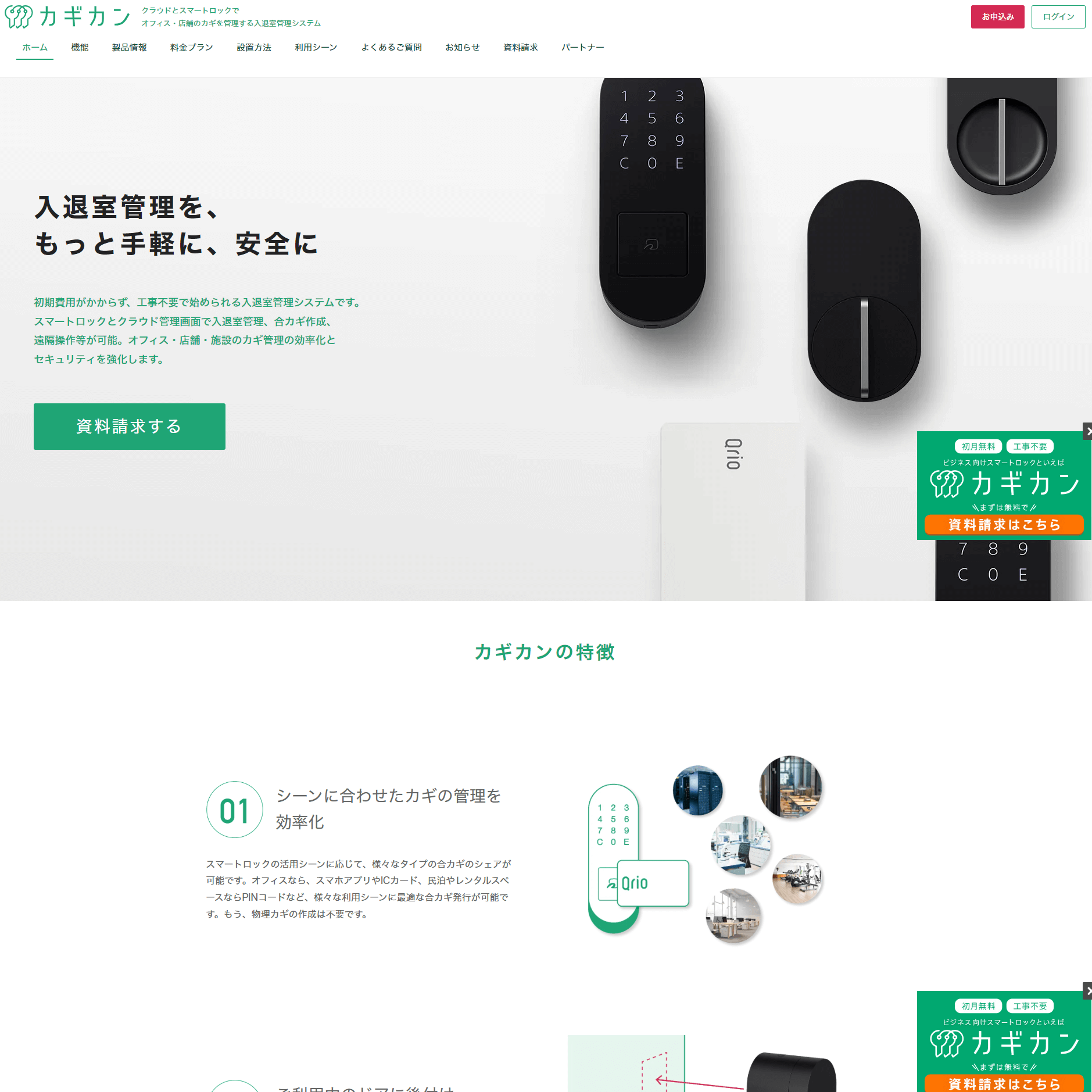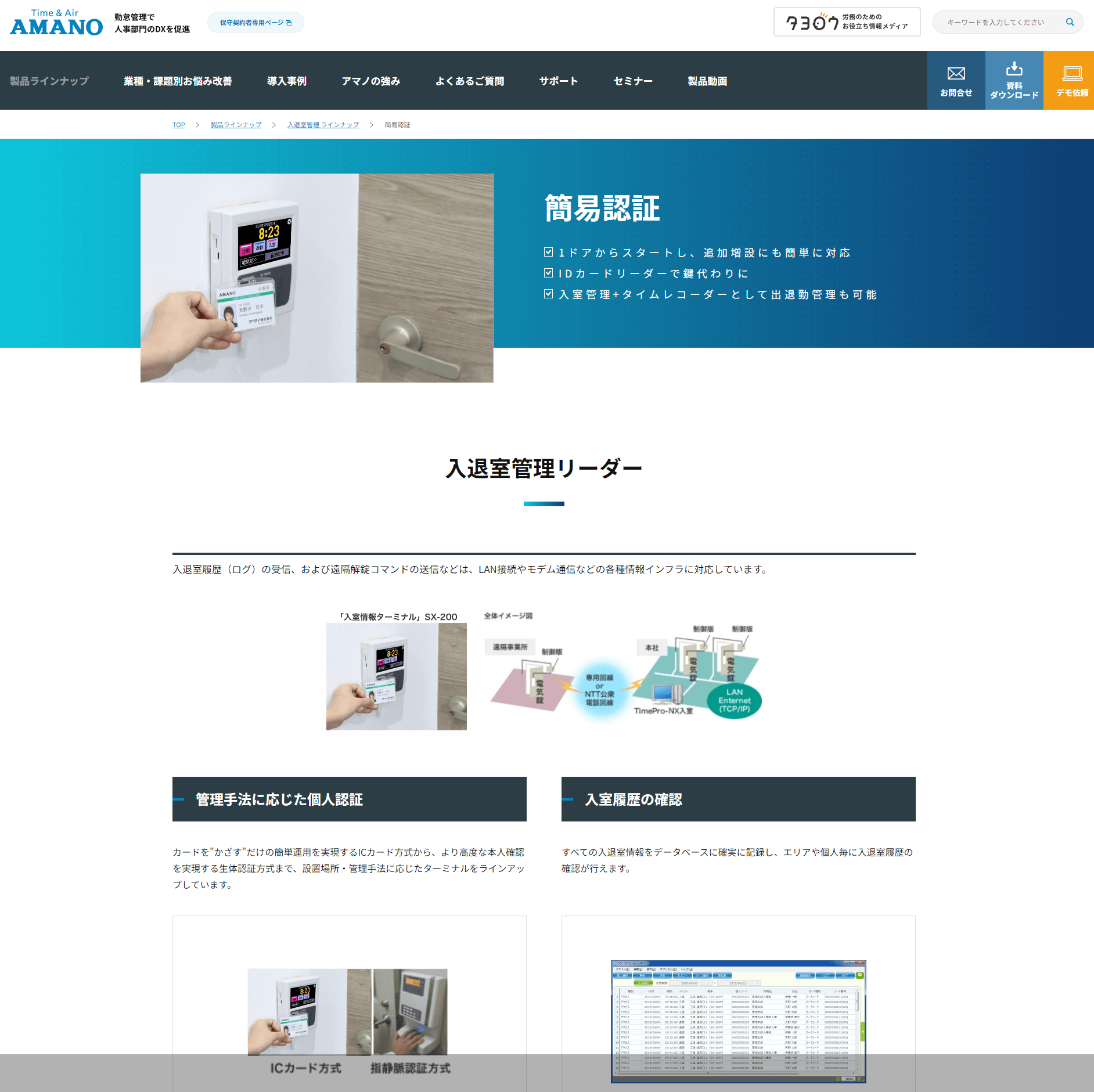はじめに
近年、働き方改革やセキュリティ意識の高まりに伴い、オフィスにおける入退室管理が大きく見直されています。その中でも注目を集めているのが、スマートフォンやICカードを使ってドアの施錠・解錠を行う「スマートロック」です。
「スマートロック」はもともと、一般家庭の玄関向けに普及が進んでいましたが、最近では企業やオフィスビルに導入し、高いセキュリティを確保しながら効率的な入退室管理を実現する事例が増えています。物理鍵の紛失リスクを軽減できたり、勤怠管理との連携で作業効率が向上したりと、多くのメリットが期待できるためです。
本コラムでは、検索キーワード「オフィス スマートロック」をテーマに、オフィス向けスマートロックの導入を検討している方に向けて、その特徴や導入メリット、注意点を詳しく解説していきます。すでにスマートロックの存在を知っていても、具体的に何を基準に選べばいいのかわからない、あるいはコスト面やセキュリティ面の課題が気になる…といった悩みをお持ちの方も多いでしょう。本記事を読むことで、スマートロック導入の検討材料をより深く把握し、自社に最適な選択をするヒントを得ていただければ幸いです。
CONTENTS
スマートロックとは
スマートロックの定義
スマートロックとは、物理鍵を使用せずに、スマートフォンやICカード、テンキー(暗証番号入力)などでドアの施錠や解錠を行えるシステムを指します。通常はドアや門扉のサムターンに取り付け、BluetoothやWi-Fiなどを通じて通信し、自動でサムターンを回して鍵の開け閉めを行います。
スマートロックで利用される代表的な認証方式
・スマートフォンアプリ型:スマホに専用アプリをインストールし、アプリから解錠操作を行う
・ICカード型:社員証や入館証などのICチップを読み取って解錠する
・テンキー型:スマートロック本体に設置されたテンキーに暗証番号を入力して解錠する
・生体認証型:指紋や顔認証などを利用して解錠する(オフィス向けでは一部導入例あり)
なぜスマートロックが注目されるのか
スマートロックが注目を集める背景には、セキュリティ意識の高まりだけでなく、働き方やオフィス環境の変化が挙げられます。リモートワークやフレックス制度の普及により、社員の出入りが不規則になったことで、オフィスの入退室管理を効率化したいというニーズが強まったのです。
また、従来の物理鍵による管理では、鍵を紛失したり、社員の退職時に鍵の回収を忘れてしまったりといったヒューマンエラーが発生しやすいという課題がありました。スマートロックであれば、紛失した社員証やスマートフォンの権限をシステム上で即時に無効化できるので、管理負荷が大幅に軽減されるメリットもあります。
スマートロックの種類
スマートロックは大きく分けると、「電子錠」と「電気錠」の2つのタイプがあります。どちらも物理鍵を使わずに施錠・解錠を行う点は同じですが、取り付け方法やセキュリティレベルが異なります。オフィスへの導入を検討する際は、それぞれの特徴を正しく理解し、自社のオフィス環境に適したタイプを選ぶことが重要です。
簡単に設置できる「電子錠」
「電子錠」は後付けで取り付けられるスマートロックのことを指します。一般的には以下のような特徴があります。
・工事不要:両面テープや簡易的なビス留めなどで取り付けが可能
・コストを抑えやすい:設置工事が不要なため、初期費用が安価
・賃貸オフィスでも導入しやすい:退去時に原状復帰が求められる場合でも取り外しが容易
一方で、後付けゆえのリスクとして、「強度が十分でない」「外から簡単に外せてしまう」といった不安を抱えるケースもあります。実際に防犯上の対策として問題ないかどうかは、製品の設計や取り付け方法によって大きく変わるため、信頼性の高いメーカー製品を選ぶことがポイントです。
電子錠が適しているケース
・小規模オフィスや個人事務所など、施工工事に大きなコストをかけたくない場合
・テナントオフィスで、原状復帰条件が厳しく、大規模工事が難しい場合
・副業・スタートアップなど、まずはスモールスタートでスマートロックを試したい場合
セキュリティをさらに強化する「電気錠」
「電気錠」は、ドア自体に専用の機構を組み込む形でスマートロックを導入するタイプです。一般的に、オフィスビルのエントランスや大規模オフィスの主要扉に使われることが多く、以下のような特徴があります。
・工事が必要:ドアや壁に穴を開け、配線を通すなどの施工が欠かせない
・高い耐久性・防犯性:簡単に外れる心配が少なく、長期運用に向く
・メーカーの保守サービスが充実:故障時や不具合発生時に迅速なサポートを受けられる
導入時には、施工費用や工期が発生するため、初期投資が大きくなる点がネックといえるでしょう。しかし、多くの人が出入りするビルや高額な機密情報を扱うオフィスでは、物理的にも強固な構造を持つ電気錠のほうが安全性が高いため、結果的に安心感を得やすい場合があります。
電気錠が適しているケース
・大規模オフィスやビルのエントランスなど、重要な出入口のセキュリティを確保する必要がある場合
・機密データを扱う部署やサーバールームなど、非常に高いセキュリティレベルが求められる場合
・物件に対する長期契約があり、施工工事を行っても長期間利用できる環境である場合
オフィス向けスマートロックの特徴
家庭向けとの違い
家庭向けスマートロックは、玄関ドアに後付けし、荷物を持ったままでもスマホひとつで解錠できるといった利便性を重視しています。防犯面では、外出先から解錠状態を確認できたり、子どもの帰宅を履歴でチェックできたりといった機能が一般的です。
一方、オフィス向けスマートロックは、主に以下の点で家庭用と異なる高機能を備えることが多いです。
1.エリアごとの入退室制限機能:部署や部屋ごとにアクセス権限を細かく設定できる
2.利用履歴の詳細管理:誰が、いつ、どの扉を通過したかをリアルタイムで確認可能
3.外部システムとの連携:勤怠管理システムや警備システムなど、ビジネスシーンを想定した連携機能
このように、オフィス向けスマートロックは「複数ユーザーが日常的に利用し、且つセキュリティや権限管理が厳格に行われる」環境を想定しているため、企業が利用しやすい仕組みが整っています。
反応速度や履歴共有の重要性
家庭用のスマートロックをオフィスに導入したケースで、反応速度が遅くてストレスを感じたり、履歴がクラウドに正常に反映されないために社員の勤怠情報と連携できない、という声が上がることがあります。オフィスでは多くの人が一斉に出勤退勤を行うケースがあるため、解錠・施錠のスピードや確実な履歴管理が求められます。
もし家庭向けのスマートロックを活用する場合でも、同時接続に強いかどうかや認証方式がオフィスの運用に合っているかといった点を十分に吟味しましょう。とはいえ、企業規模が大きかったり、要件が複雑であれば、オフィス向けスマートロックのほうが無難です。
オフィス向けスマートロックの導入メリット
セキュリティを強化し、防犯対策に効果的
オフィス向けスマートロックの最大の利点のひとつは、セキュリティの強化です。具体的には、以下のような点で防犯対策に役立ちます。
・エリアごとの施錠・解錠管理
たとえば、一般社員は執務室Aには入れるが、サーバールームBにはアクセスできないようにするといった、きめ細かな権限設定が可能です。さらに管理者アカウントを使えば、離れた場所からでもアクセス権の付与・取り消しができます。
・オートロック機能
人為的な鍵の閉め忘れを防ぐため、扉が閉まって一定時間が経過すると自動で施錠する機能が搭載されている製品も多いです。これにより、ヒューマンエラーが原因となる不正侵入リスクを低減できるでしょう。
・来訪者への一時権限発行
来客や業者が訪れる際に、必要な時間やエリアだけ一時的に解錠権限を付与することができます。従来は物理鍵の受け渡しが必要でしたが、その手間とリスクを削減可能です。来訪者は専用アプリの招待リンクや発行されたICカードなどで入退室ができ、用が済んだ後はすぐに権限が失効します。
オフィス内の個人情報保護に貢献
社員や顧客の個人情報が詰まった書類やデータ、あるいは企業の極秘資料を取り扱うオフィスにおいて、情報漏えいリスクを抑えることは経営上の最重要課題のひとつです。オフィス向けスマートロックを用いて入退室を厳格に管理することで、次のような効果が期待できます。
・部外者の不正な立ち入りを防ぎ、管理者以外アクセス不可のエリアを確実にロックできる
・特定の社員にのみアクセス権を与え、情報資産を最小限の範囲で守る
・万が一問題が起きた際も、入退室履歴を追跡して原因を突き止めやすい
企業の規模が大きくなるほど、扱う情報が増えていきます。スマートロックにより、セキュリティと利便性を両立した環境構築が見込めるのは大きなアドバンテージと言えるでしょう。
鍵管理が不要になる
従来の物理鍵では、社員やアルバイトに鍵を配布したり、退職時に回収したりする作業が発生します。配布や回収にかかる手間・コスト、さらに紛失や盗難のリスクなど、多くの煩雑さがありました。スマートロックなら、以下のように管理をシンプルにできます。
・物理鍵そのものが存在しないので、紛失・破損・複製のリスクが激減
・新規社員へのアクセス権は、システム上ですぐに付与・削除が可能
・退職者がいた場合も、即時に権限を取り消すだけでよく、回収の手間が省ける
また、会社支給のスマートフォンを利用している社員が多い場合、端末管理と鍵管理を一元化できるため、管理コストの最適化にもつながります。
勤怠管理・業務効率の向上
オフィス向けスマートロックには、入退室ログを記録し、それを人事労務システムと連動させる仕組みがある製品が多くあります。これにより、タイムカードやICカードの打刻漏れといった人為的ミスを防ぎ、次のような効果が期待できます。
・正確な出退勤時刻が自動記録されるため、勤怠管理業務がスムーズに
・システム上ですべて管理できるので、経理・総務担当者の事務作業が軽減
・リモートワークと出社を織り交ぜる「ハイブリッド勤務」の場合にも、出社した日・出社時刻を正確に把握できる
企業によっては、これを機に「タイムカードを廃止し、すべてスマートロックによる打刻データで勤怠を管理する」というケースも増えています。不正打刻も物理的に困難になるため、従業員・企業双方にとってメリットが大きい仕組みと言えるでしょう。
オフィス向けスマートロックの導入デメリット
利便性やセキュリティの向上など多くのメリットがあるスマートロックですが、注意すべきデメリットやリスクも存在します。事前に把握しておくことで、導入後のトラブルや想定外のコスト発生を防ぐことができます。
コストがかかる
・初期導入費用:工事が必要な電気錠の場合、ドアや壁の加工費、配線費が高額になる可能性がある
・運用コスト:月額のシステム利用料、保守サポートの契約、必要に応じたアップデート費用など
・買い替え・再設置コスト:製品寿命や技術進歩により、数年ごとに新しいシステムへ移行する場合がある
特に電気錠では、セキュリティ向上のための投資と割り切る考え方が必要です。スマートロック導入により得られる業務効率化やセキュリティリスク低減が、コストに見合うリターンかどうかを事前に試算し、経営判断を下すことが重要となります。
電池切れに注意
電子錠タイプの場合は、電池切れや充電切れになると、ドアが開閉できなくなる可能性があります。また、スマートフォンアプリ型であっても、端末自体の電池が切れてしまえば解錠が難しくなるケースもあります。
・定期的なバッテリー交換や充電が必要
・スマートフォンを持たずに出社した社員が増えると、オフィスへの入室に手間取り、問い合わせが増える可能性がある
対策としては、電池残量アラート機能やバックアップキーの導入などが挙げられます。また、利用者全員が定期的にデバイスの電池残量を意識するよう、周知徹底を行うことも大切です。
オフィス向けスマートロックの選び方
オフィス向けスマートロックを導入する際には、以下のポイントを総合的に判断して最適な製品を選びましょう。企業の規模や業種、セキュリティ要件、予算感によって、選ぶべきスマートロックが変わってきます。
自社のドア形状・構造に合うスマートロックを選ぶ
オフィスのドアには、開き戸や引き戸、ガラス扉などさまざまな種類があります。スマートロック製品ごとに対応できるドア形状が異なるため、設置可能なドアタイプを確認することが最初のステップです。
・引き戸用のアタッチメントがあるか
・ガラス扉でも取り付けられる製品があるか
・ドア枠やサムターン周りに十分なスペースが確保できるか
また、ドアの厚みや材質によっても、設置可否が変わる場合があります。製品の仕様書やメーカーサイトをよくチェックし、導入前に現地調査を行うと安心です。
認証方式を確認
オフィス向けスマートロックでは、スマートフォンアプリ認証、ICカード認証、テンキー認証、生体認証など、複数の認証方式が用意されていることが多いです。自社の運用に最もマッチする方法を選ぶために、以下の点を検討しましょう。
・スマートフォンアプリ認証: 社員全員がスマホを所持しているか、業務でスマホを常に使うか
・ICカード・社員証認証: 既存の社員証を利用できる場合、追加コストを抑えられる
・テンキー暗証番号: 端末不要だが、暗証番号の使い回しや漏洩リスクに注意
・生体認証: 指紋や顔認証など高いセキュリティを実現するが、導入コストが割高になりやすい
セキュリティを重視するのであれば、複数の認証方式を組み合わせた「多要素認証」が有効です。たとえばICカードと暗証番号の両方を必要とする仕組みにすれば、カードの盗難や番号漏洩だけでは解錠できないため、格段にセキュリティレベルが上がります。
データ登録のしやすさ
スマートロック導入後は、社員それぞれの権限をシステムに登録する必要があります。従業員数が多い企業では、登録作業の負荷が大きくなる可能性があるので、以下の機能をチェックするとよいでしょう。
・一括インポート機能: 人事データや従業員一覧をCSVなどでまとめて取り込めるか
・API連携: 既存の人事労務システムとAPI連携を行い、自動的に登録・削除が行われるか
大規模企業の場合、登録作業を手動で行うと管理担当者の負担が非常に大きくなります。逆に10名以下の小規模オフィスなら、あまり問題にはならないかもしれません。自社の従業員数や運用体制を踏まえて検討してください。
耐用年数やバッテリー寿命
スマートロックには、一般的な錠前と同様に耐用年数が存在します。日本ロック工業会の規定では電気錠の耐用年数を「7年」とされていますが、これはあくまで目安であり、メーカーごとに推奨する交換時期や保証期間が異なる場合があります。
・製品自体の物理的な寿命
・ソフトウェアやサーバーシステムの更新サイクル
・バッテリー内蔵式の場合はバッテリー交換の目安
長く安心して使うためには、定期的なメンテナンスやメーカーの保守契約を検討することが重要です。また、バッテリー寿命は利用頻度や開閉回数によって大きく変動するため、想定使用シーンとズレがないかを確認しましょう。
サポート体制の充実度
万が一のトラブル発生時に、迅速かつ的確に対応してもらえるかどうかは、オフィス向けスマートロックを選ぶ際の大きな決め手になります。オフィスの主要入口が使えなくなると業務に直結する支障が出るため、サポート体制がしっかりしている製品を選ぶことが望ましいです。
・24時間365日の電話サポートや駆けつけサービスがあるか
・規模拡張時や機能追加時にコンサルティングをしてもらえるか
・導入実績が豊富で、システム障害が起こった場合の解決スピードが速いか
メーカーやベンダーの評判や口コミを調べ、導入後も長期的に付き合っていけるパートナーを選ぶ意識を持ちましょう。
オフィス向けの入退室管理システムおすすめ3選
idoors

idoorsのおすすめポイント
様々な認証リーダーに対応!ニーズに合わせた対応が可能!
さまざまな業種や規模のオフィスに対応できるよう、柔軟なシステム設定が可能!
導入前後のサポート無料! ヒアリング~設定までしっかりフォロー!
idoorsの基本情報
| 会社名 | 株式会社エーティーワークス |
| 住所 | 東京本社:〒106-6137東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー37F |
| 電話番号 | 03-3497-0505 |
| 電源の種類 | 電気錠 |
| 解錠方法 | 暗証番号、ICカード、スマートフォン、生体認証 |
| 価格 | 1万1,000円〜※電気錠のため初期費用は別途 |
導入事例
-

引用元:https://idoors.jp/株式会社SmartHR様- 利用者数
- 300人~
- 導入目的
- セキュリティ強化/入退ログの把握
-

引用元:https://idoors.jp/株式会社生活総合サービス様- 利用者数
- 51人~100人
- 導入目的
- セキュリティ強化/入退ログの把握/既存システムのリプレイス/顔認証の入退
-

引用元:https://idoors.jp/ゾーホージャパン株式会社様- 利用者数
- 101人~300人
- 導入目的
- 入退ログの把握/自社システムとの連携/複数拠点の一括管理
idoorsは、解錠・施錠の動きを電気信号によって行う電気錠タイプの入退室管理システムであり、電池式ではないのが特徴です。電源からの配線で動くため、取付に工事が必要になりますが、安定稼働ができ、さらに防犯性が高いなどのさまざまなメリットがあります。
いつでもクラウドの管理ツールで記録を確認できる
ドアの開閉がクラウド管理できるようになり、しかも複数の拠点の管理方法を一元管理できるようなります。
充実機能で課題を解決!
idoorsで入退室管理できるようになれば、ISMS、Pマークも取得も可能であり、勤怠管理もより効率的にできる様になるのです。
idoorsの最大の魅力と言えるのが抜群のセキュリティ機能です。管理画面からさまざまな情報を把握でき、アルタイムで入退室や在室状況をいつでもチェック可能です。
さらにユーザー単位で入退室できるドアの制御が可能なので、気密性が高いようなデータを保管する部屋に導入するものおすすめでしょう。クラウド型入退室管理システムであり、拠点が離れていても一元管理できるのがidoorsです。
電気錠タイプだからこそのメリットとは
WEB上の管理画面より遠隔で解錠も可能なので、急な解錠申請および予定外の訪問にも即時対応できます。顔認証にも対応しており、マスクしていても認証可能です。非接触認証が可能なので、衛生面にも優れています。
ALLIGATE

ALLIGATEのおすすめポイント
専門の作業員が責任をもって設置!
社内ネットワークの構築不要!
導入~運用まで手厚くサポート!
ALLIGATEの基本情報
| 会社名 | 株式会社アート |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-25-11 五反田一丁目イーストビル |
| 電話番号 | 記載なし |
| 電源の種類 | 電気錠 |
| 解錠方法 | 暗証番号、ICカード、スマートフォン |
| 価格 | 1扉あたり1万6,500円 ※電気錠のため初期費用は別途 |
導入事例
-

引用元:https://alligate.me/akippa株式会社- 利用者数
- 50人~299人
- 導入目的
- 入退室管理/セキュリティ強化/社員のタイムコスト意識にも好影響
-

引用元:https://alligate.me/株式会社ミュートス- 利用者数
- 10人~49人
- 導入目的
- 最新機器の導入/入退室・勤怠管理
-

引用元:https://alligate.me/株式会社ランディックス- 利用者数
- 50人~299人
- 導入目的
- セキュリティー強化/入退室管理一元化/手軽なシステムの導入
セキュリティ専業メーカーのクラウド型入退管理システムがALLIGATEです。瞬時に開場でき電池交換が不要でWi-Fi環境も不要、駆けつけサポートもあり、スマホアプリにも対応しているといったさまざまなメリットがあります。
セキュリティ専業メーカーのシステムだから高機能
セキュリティ専業メーカーだからこその高いセキュリティ性に注目です。両面テープで取り付けるだけの製品ではなく、落ちてしまったり剥がれてしまったりする心配はありません。専門の作業員が責任を持って設置してくれるので安心です。
一元管理可能なハイセキュリティ環境をつくる
ALLIGATEは、LTE内蔵の通信機器を利用したクラウド型のサービスです。社内ネットワークへ接続したり、拠点間のネットワークを構築したりする必要はありません。煩雑な手続き不要で、一元管理可能なハイセキュリティ環境を作れるのです。
勤怠管理システムと連携することで、ALLIGATEで取得した入退室ログを出退勤情報として自動送信できます。予約システムとの連携時には、予約完了時に入室可能なカギを発行してくれるなど、さまざまな機能も兼ね備えています。
さらに防犯カメラとの連携も可能で、遠隔管理やALLIGATEのAPIを活用し自社システムと連携することも可能です。
全国どこでも手厚くサポートしてくれる
初めての入退室管理リスステムの導入となると、分からないことだらけで不安に感じることもあるでしょう。その点、ALLIGATEでは、24時間365日のサポート体制を構築しています。万が一の故障の際には製品保証もあるので、余計なコストがかかることもありません。
しかも、契約期間中の故障は経年劣化が原因であったとしても無償で機器交換してくれます。サポートも日本全国対応なので安心です。
カギカン

カギカンのおすすめポイント
設置はドアに簡単貼付けるだけ!
オートロック機能搭載! カギの締め忘れによる盗難・情報漏洩リスクを防止!
最短3営業日で導入可能!
カギカンの基本情報
| 会社名 | Qrio株式会社 |
| 住所 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-3-4 東新産業ビル3F |
| 電話番号 | 050-3187-7481 |
| 電源の種類 | 電子錠(電池錠) |
| 解錠方法 | 暗証番号、ICカード、スマートフォン |
| 価格 | カギカンコンソールのみ 月額4,500円~ カギカンBasicプラン 月額5,900円~ カギカンProプラン 月額7,300円~ ※利用者料金は利用人数20人までは無料となり、21人目から100円/人で追加費用 |
導入事例
-

引用元:https://kagican.jp/株式会社コスモスさま- 利用者数
- 5人~10人
- 導入目的
- 入退室履歴の取得/履歴の長期保存/施錠忘れ
-

引用元:https://kagican.jp/株式会社ナインブロックさま- 利用者数
- 10人~20人
- 導入目的
- 従業員数に対する合カギの不足/テレワーク時における煩雑なカギの受け渡し
-

引用元:https://kagican.jp/リンクウィズ株式会社さま- 利用者数
- 10人~50人
- 導入目的
- 物理カギの不足/カギを受け渡す手間/入室時・退室時の履歴把握
初期コストを重視しているなら、カギカンがおすすめです。工事不要で始められる入退室管理システムであり、スマートロックおよびクラウド管理画面で入退室管理や合鍵作成、遠隔操作などができます。より効率的にオフィスなどを運営していきたいと考える方に適しているのがカギカンなのです。
シーンに合わせてカギの管理を効率化
スマートロックの活用シーンはさまざまであり、そのさまざまなシーンに対応できるのがカギカンです。さまざまなタイプの合鍵のシェアが可能であり、オフィスならスマホアプリやICカードが利用でき、民泊およびレンタルスペースであれば、PINコードなど利用心に最適な合鍵を発行できるのです。
いつ・誰が入退室したか確認できる
セキュリティ機能もしっかりとしており、カギカン管理コンソールでカギの解施錠履歴およびドアの入退室履歴が残ります。管理画面からの複数ドアの一元管理も可能です。ドアが閉まったタイミングでオートロックする機能もあるため、利用者の鍵の閉め忘れによる盗難および情報漏洩のリスクも低減できます。
工事費無料!低コストで利用できる
カギカンは、初期導入費用、工事費用は無料です。初期費用がかからず、さらに利用開始月は無料期間なので、コストゼロでお試し利用できるのです。それでいて複数ドアに対応しているので、とりあえず入退室管理システムを導入したいと考えている方に利用に適しています。
まとめ
オフィスにおけるセキュリティ強化や入退室管理の効率化を考えるうえで、「オフィス スマートロック」は非常に魅力的な選択肢となり得ます。物理鍵が不要になることで、煩雑だった鍵管理を一気にデジタル化でき、部外者の不正侵入リスクや社員の鍵紛失リスクを大幅に軽減できます。
また、勤怠管理システムやセキュリティシステムとの連携によって、打刻漏れの防止や従業員の入退室データの正確な取得が可能となり、業務効率も格段に上がるでしょう。一方で、工事コストや月額利用料、バッテリー切れなどの注意点もあるため、メリットとデメリットをしっかり比較検討することが大切です。
導入を決める際は、自社オフィスのドア形状や求めるセキュリティレベル、従業員数、運用体制などを整理し、最適なスマートロックを選びましょう。実際に複数のメーカーやサービスの見積りを取り、機能や導入費用、サポート体制を総合的に比較すると、より納得感のある選択ができます。企業規模や事業内容によって必要なセキュリティレベルは異なるため、しっかりと要件を明確化し、導入後に想定されるメリットとコストを見極めてください。
【FAQ】よくある質問
- オフィス向けスマートロックの導入費用はどのくらいかかりますか?
- 導入費用は電子錠と電気錠で大きく変わります。電子錠は工事費がほぼ不要なため、製品本体が数万円~数十万円程度で済むケースが多いですが、電気錠はドアや壁に配線を通す施工が必要となるため、数十万円~100万円前後の予算が見込まれることもあります。さらに、クラウドサービスの月額利用料や保守費用がかかる場合もあるので、必ず見積りを複数社から取りましょう。
- スマートロックは停電時や電池切れ時でも解錠できますか?
- 多くのスマートロック製品には、緊急時の物理鍵やバックアップ電源が用意されています。電子錠タイプの場合は電池切れに備えて、外からモバイルバッテリーで給電して開錠できる仕組みを持つものもあります。電気錠タイプは建物の非常用電源などに接続している場合が多いため、停電時にも一定時間は稼働できる設計が一般的です。導入前に必ず非常時の対応方法を確認しましょう。
- 一度導入したスマートロックを他のオフィスへ移設できますか?
- 「電子錠」タイプであれば、両面テープやネジでの固定が主なので比較的容易に取り外して移設できます。ただし、「電気錠」タイプはドアや壁を加工しているため、移設には再び工事が必要となり、同じドアでなければ取り付けが難しい場合もあります。移転やリニューアルの可能性があるオフィスでは、導入時に施工コストや移設リスクも検討しておくと安心です。
- スマートロックで勤怠管理や打刻を完全に代替できるのでしょうか?
- オフィス向けスマートロックの多くは、出入りの履歴をクラウド上に記録し、勤怠管理システムと連携できるAPIを持つものがあります。これらを活用すれば、打刻専用のシステムやタイムカードを使わずとも、社員の出退勤記録を自動取得することが可能です。ただし、社員が扉を開けずに内線や別ルートから入室するなど、運用上のイレギュラーを想定する必要もあります。完全な代替を目指すなら、オフィスレイアウトや運用ルールの整備が不可欠です。
- セキュリティ面で特に注意すべき点は何でしょうか?
- スマートロック導入後も、セキュリティポリシーの策定や周知徹底が非常に重要です。たとえば、テンキー認証の場合は定期的に暗証番号を変更する、ICカードを紛失したら即時に権限を無効化する、管理者アカウントのパスワードを強固にするなど、人間側のセキュリティ意識が欠かせません。また、ベンダーが提供するソフトウェアのアップデートを怠ると脆弱性を突かれる恐れがあるため、アップデートのスケジュールやサイバーセキュリティ対策にも気を配りましょう。